
日本の選挙権の拡大の歴史を
選挙権と被選挙権
衆議院と貴族院(参議院)
に分けてわかりやすく表にしてください

以下に、日本の選挙権拡大の歴史を
「衆議院」と「貴族院(参議院)」 に分け、選挙権と被選挙権の変遷を表にまとめました。
人口データは歴史的統計に基づく概算値です(※資料によって差異あり)。
日本の選挙権の拡大と貴族院
日本の選挙権拡大の歴史
| 年 | 区分 | 選挙権 | 被選挙権 | 有権者数 /人口比率(概算) | 主な変更点・背景 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1889 | 衆議院 | 男性のみ 25歳以上 15円以上納税者 | 30歳 | 約40万人 約4,000万人の1% | 大日本帝国憲法制定 「制限選挙」で富裕層のみが投票可能 |
| 貴族院 | 非公選 (皇族・華族・勅選議員など) | 非公選 | 0人 | 貴族院は終身制 | |
| 1900 | 衆議院 | 10円以上に緩和 | 30歳 | 約88万人 約4,400万人の2% | 日露戦争前の政治改革 |
| 貴族院 | 非公選 | 非公選 | 0人 | 変更なし | |
| 1925 | 衆議院 | 納税要件廃止 (普通選挙法) | 30歳 | 約1,200万人 約6,000万人の20% | 普通選挙法成立 (女性は依然除外) |
| 貴族院 | 非公選 | 非公選 | 0人 | 変更なし | |
| 1945 | 衆議院 | 男女平等 20歳以上 (普通選挙) | 25歳 | 約3,600万人 約7,200万人の50% 成人人口の約80% | 女性参政権実現 GHQ主導の民主化政策 |
| 貴族院 | 廃止(1947年) | 廃止 | – | 貴族院廃止と参議院設置 GHQ主導の民主化政策 | |
| 1947 | 参議院 | 男女平等 20歳以上 | 30歳 | 約3,800万人 約7,800万人の49% | 参議院は「良識の府」として設計 |
| 2015 | 衆議院 | 18歳以上 | 25歳 | 約1億160万人 約1.27億人の80% (18歳以上人口) | 選挙権年齢70年ぶり引き下げ 若年層の政治参加促進 |
| 参議院 | 18歳以上 | 30歳 | 同左 (衆議院と同数) | 衆議院と同時改正 |
補足説明
- 貴族院と参議院の違い
- 貴族院(~1947年):皇族・華族・勅選議員で構成され、国民の選挙で選ばれない。
- 参議院(1947年~):公選制(比例代表+選挙区制)で「良識の府」として衆議院の暴走を抑制。
- 主な拡大のポイント
- 1925年:男性普通選挙(納税要件廃止)が実現。
- 1945年:女性参政権導入(GHQ主導の民主化政策)。
- 2015年:18歳選挙権開始(若年層の政治参加促進)。
- 現在の課題
- 被選挙権年齢(衆議院25歳/参議院30歳)の引き下げ議論が進行中。
- 在外邦人や障害者の投票環境整備が継続的な課題。
- 人口比率の算出根拠
- 1945年:成人(20歳以上)人口を総人口の約50%と仮定(当時の平均寿命・年齢構成を考慮)。
- 2015年:18歳以上人口を総人口の約80%と推定(国立社会保障・人口問題研究所データを参考)。
- 特記すべき変遷
- 1925年:男性普通選挙で有権者が一気に20%に拡大(労働者階級の政治参加が可能に)。
- 1945年:女性参政権導入で有権者数が3倍以上に急増。
- 現代の課題
- 少子高齢化で有権者数に占める高齢者の割合が増加(2022年:60歳以上が有権者の約45%)。

この表から、「選挙権拡大=民主化の進展」 と 「人口構成の変化が政治に与える影響」 が同時に読み取れます。
貴族院廃止はGHQの意向 敗戦による変更

1945 1947の選挙制度の変更はGHQの意向によるところが大きいですよね?
そこのところを説明してください。

以下、1945年と1947年の選挙制度改革におけるGHQの影響を説明します。
GHQによる民主化政策の背景
第二次世界大戦後、日本は連合国軍(GHQ)の占領下に置かれました。GHQは、日本の軍国主義と封建的制度を解体し、民主主義の基盤を築くことを目的に、以下の選挙制度改革を主導しました。
1945年:女性参政権の導入と普通選挙の確立
GHQの直接指示
- ポツダム宣言受諾直後、GHQは「五大改革指令」(1945年10月)を発令。
その第4項で「女性解放と参政権付与」を明確に要求。 - 旧体制の打破:
財産や性別による選挙権制限を撤廃し、「普通選挙」を実現。
具体的な変更点
- 女性参政権(1945年12月改正)
- それまで選挙権がなかった女性に20歳以上の選挙権を付与。
- 被選挙権も認められ、1946年の総選挙では39名の女性議員が誕生。
- 納税要件の廃止
- 男性の納税額による制限を撤廃し、全成年男性に選挙権を拡大。
GHQの狙い
- 封建的家制度の解体:
女性の社会進出を促進し、家族内の権力構造を変革。 - 民主主義の浸透:
国民全体が政治に参加する意識を育成。
1947年:日本国憲法施行と参議院設置
GHQ草案の影響
- 日本国憲法の草案は、GHQ(特に民政局)が作成し、日本政府に提示。
第15条で「普通選挙の保障」を明記。 - 貴族院廃止:
封建的階級制度の象徴だった貴族院を廃止し、公選制の参議院を設置。
参議院の設計思想
- 「良識の府」としての役割:
GHQは衆議院の暴走を防ぐため、参議院を「冷静な再考機関」として設計。- 被選挙権年齢を30歳以上に設定(衆議院より高齢層を想定)。
- 任期6年(衆議院の2倍)で、解散なしの安定性を重視。
GHQの意図
- 二院制の民主化:
非公選の貴族院を廃し、国民の意思を反映した制度へ転換。 - 保守層の懐柔:
参議院に「穏健な保守勢力」を期待し、急進的改革を抑制。
GHQの影響力の具体例
- 選挙法改正の強制
- 日本政府はGHQの要求を拒否できず、1945年改正はわずか2か月で成立。
- 憲法草案の直接関与
- 参議院の制度設計は、GHQ民政局のチャールズ・ケーディスらが主導。
- 女性議員の誕生促進
- GHQはメディアを通じて女性の立候補を奨励し、婦人参政権運動家を支援。
歴史的評価
- 肯定的側面:
封建的制度の解体と民主主義の基盤構築に貢献。 - 批判的側面:
「押し付け憲法」論争の源となり、日本人の自主的な制度設計が制限された。
まとめ
- 1945年:GHQの指令で女性参政権と普通選挙を即時導入。
- 1947年:GHQ草案に基づき貴族院を廃止し、参議院を創設。
- 結果:日本の民主化を加速させたが、GHQの「外圧」としての側面も残した。

この改革は、現代日本の選挙制度の基盤を形作りましたが、その過程でGHQの強い影響下にあったことは事実です。

国家の主権者というか
どういう国にしていくかという事を考える人達っていうのはある程度、
担い手に一貫性がなきゃいけないはずなのだ。
だから、今の日本が官僚主導になってしまうのは『政治家の方が取り替え可能性が高いから』というのもあると思うのだよね。そこをイーロン・マスクとかは民主的に選ばれていない組織が権力を持ちすぎだと批判しているけども、僕はそれは民主主義絶対思想で偏った物の見方だなって思うのだよね。 元々だれか一貫性のあるビジョンを持つ主体が国家の在り方に大きな影響を及ぼしてきたのが歴史的にどこの国をみたってそうなんだから、民主主義的なプロセスで選ばれた代表が全てを決めるというのでは世の中うまくいかないんじゃないのかな?って思うのだよね。
僕は貴族院で良くね?って思うんだけど、これはあまり受け入れられない意見みたい。
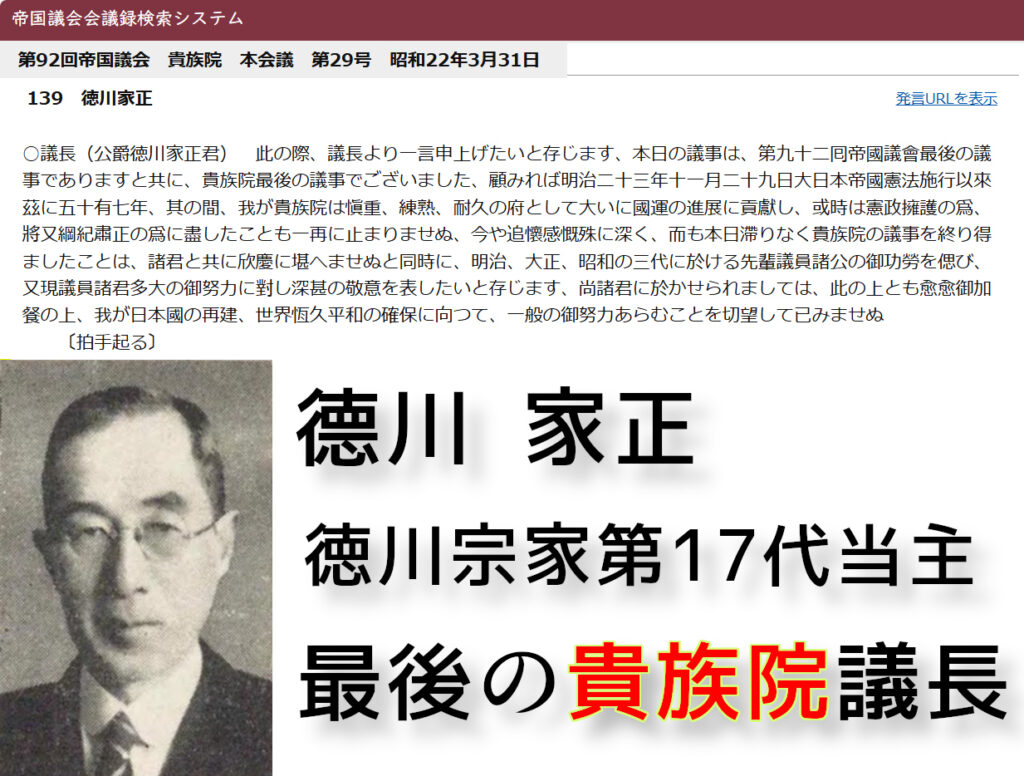
第92回帝国議会 貴族院 本会議 第29号 昭和22年3月31日 | テキスト表示 | 帝国議会会議録検索システム

だから僕は官僚主義自体は貴族院を廃止したからには仕方がないと思っていて、官僚主導もダメと官僚の権力を弱めた所で、ポピュリズムに抗えない民主主義=メディアをコントロールする者が支配する政治になっちゃうような気がするんだよね。
それを防ぐためには…
官僚の権力を弱めるなら、政治家の権力を強めないと怖い。
つまり参議院を貴族院相当に戻す方向で制度変更していく必要があると思うのだよね。
で、貴族院は1947まであった訳だけど、GHQが主導して世襲制(貴族院)から公選制(参議院)になった。
※厳密には日本の貴族院は世襲制だけではなく
皇族・華族(世襲)+勅選議員(非世襲の学者・功労者)で構成される非公選制。
上院(参議院相当)は貴族院➝任命制➝普通選挙みたいな変遷が多いんだけど、普通選挙になる事で、従来の意味での存在理由を失ってきている。だから僕はここに21世紀の上院の新しい存在理由として、選挙権が限定される院としての存在価値を付与する事を提案するのだ。
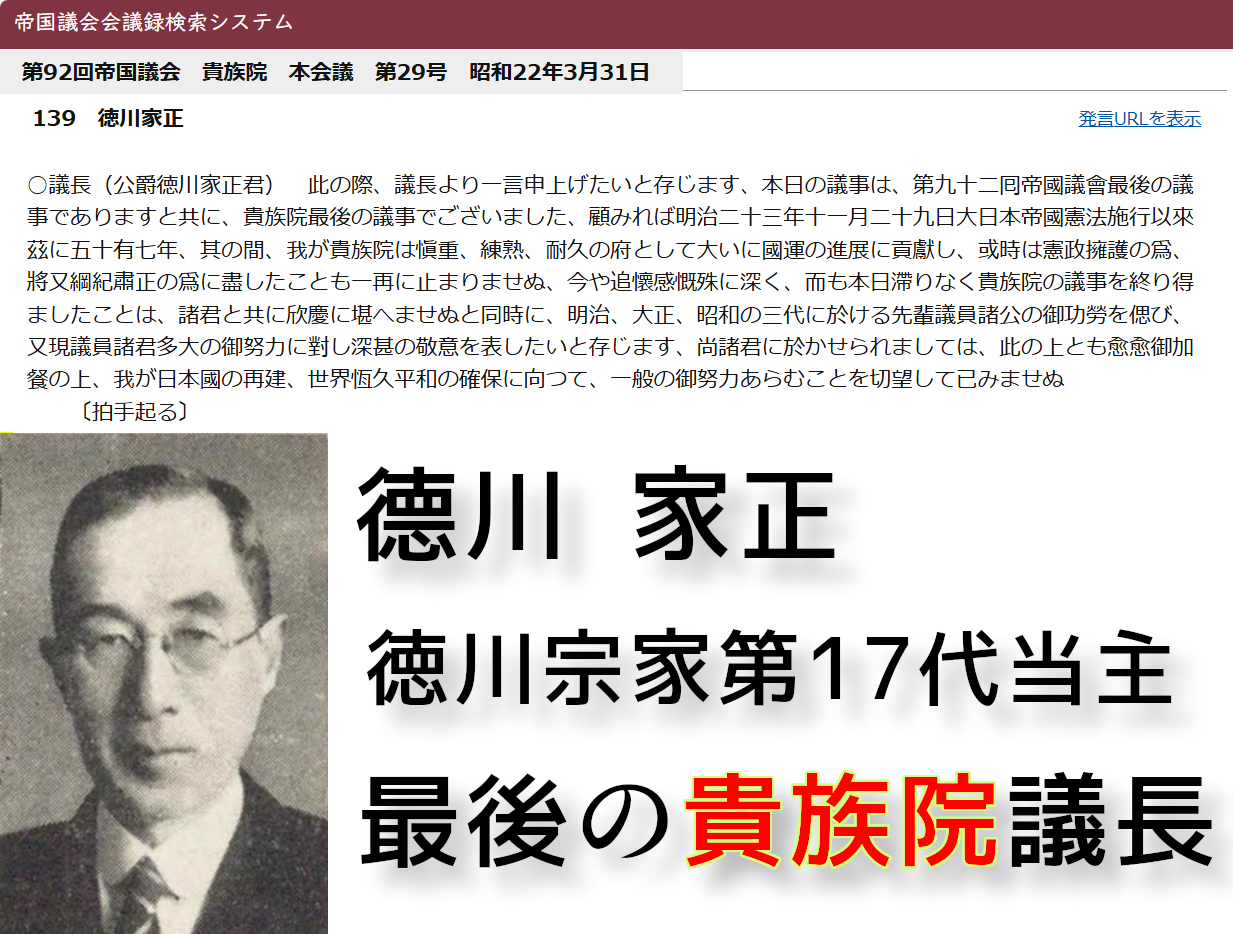
コメント